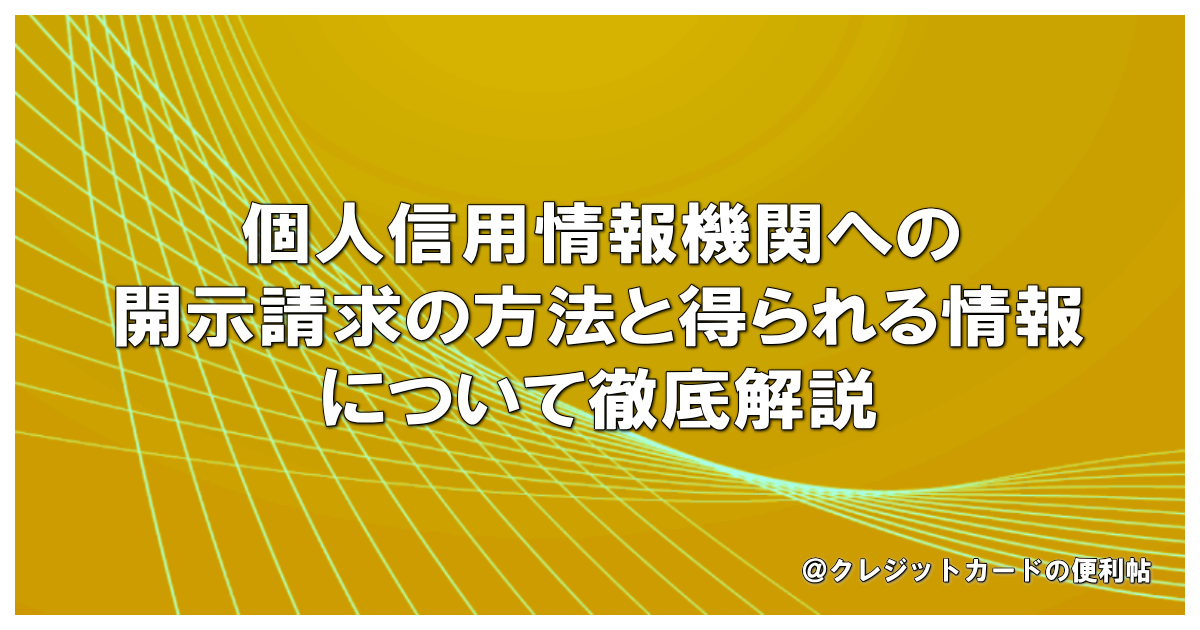個人信用情報機関には、私たちの金融商品利用情報が登録されています。
この情報は、信用情報と呼ばれており、誰でも開示請求を行うことにより、その中身を確認することが出来ます。
ただ、個人信用情報機関への開示請求となると、何だか難しいそうと感じる人も多いことでしょう。
そこで、当記事では個人信用情報機関への開示請求の方法と得られる情報について解説します。
信用情報開示請求とは?

ここでは、個人信用情報機関で行うことが出来る「信用情報開示請求」について解説します。
個人信用情報機関の役割
信用情報機関は、個人の支払い状況や契約情報などの信用情報を管理している機関です。
金融機関やクレジットカード会社が、貸付や契約などを行う際に必要な情報を提供する役割を果たしています。
これにより、金融機関が消費者に対して過剰な融資を防ぎ、各種審査を適切に行うことが可能になるのです。
また、消費者保護の観点からも重要であり、多重債務を防ぐ役割も担っています。
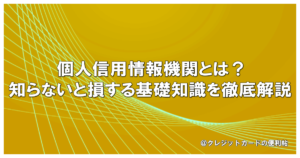
開示請求が可能な信用情報機関
現在、日本国内には主に3つの個人信用情報機関が存在しており、それぞれが異なる加盟会員を持っています。
CICは、クレジットカード会社や信販会社、携帯電話会社などが加盟しており、主に消費者向けの信用情報を取り扱います。
JICCは、消費者金融やクレジットカード会社などが中心で、似た領域をカバーしていますが、一部情報の管理内容が異なります。
KSCは、銀行や信用金庫など金融機関が加盟しており、主に住宅ローンや銀行系の借入情報を取り扱っています。
そのため、個人信用情報機関への開示請求先は、自分の取引内容に応じて選ぶ必要があります。
信用情報開示請求の基本的な流れ
個人信用情報機関へ信用情報開示請求を行うためには、まず対象となる信用情報機関を選びます。
そして、必要書類を準備してインターネットや郵送、または窓口で申請を行います。
申請後、開示請求手数料を支払うと、登録情報の照会が可能になります。
また、開示請求の結果は、郵送またはオンライン上で受け取ることが出来ます。
開示請求を行う際の注意点
開示請求を行う際には、正確な情報を提供して手続き漏れを防ぐことが重要です。
特に、本人確認書類の不備や不正確な情報記入は、開示請求の申請が遅れる原因となります。
また、手数料が発生するため、支払い方法や金額を事前に確認しておくことも必要になります。
さらに、開示報告書には個人情報が含まれるため、安全に取り扱うことに注意します。
信用情報開示の方法

ここでは、個人信用情報機関へ開示請求を行うための方法について解説します。
インターネットで開示請求する方法
インターネットを利用した信用情報の開示請求は、最も手軽で迅速に行えるため、すぐにでも信用情報を確認したい人にお勧めです。
CICやJICCでは、公式ウェブサイトに開示請求専用のページが用意されています。
そのため、事前にインターネット環境と必要な情報を準備しておくことで、その日のうちに手続きを完了することが出来ます。
そして、具体的な操作ですが、まず信用情報機関のウェブサイトにアクセスし、本人確認のための情報を入力します。
その際、運転免許証や健康保険証などの本人確認書類をアップロードする必要があります。
その後、開示請求手数料を支払いますが、基本的にはオンラインで支払います。
ちなみに、スマホ(アプリ)による申請も、インターネットで開示請求する方法に準拠します。
郵送での開示請求の流れ
郵送による開示請求は、インターネットが苦手な人や書類の控えを手元に残しておきたい人にお勧めの方法です。
信用情報機関のウェブサイトから開示請求書をダウンロードし、必要事項を記入します。
そして、必要書類(運転免許証やパスポートのコピーなど)を準備し、手数料分の収入証紙や郵便料金を添えて指定の宛先に送付します。
ちなみに、手続きが完了するまでは数日から1週間程度の時間が掛かります。
ただ、開示請求の結果は郵送で受け取ることが出来るため、安心して行うことが出来ます。
手数料と必要書類について
個人信用情報機関へ信用情報開示請求を行う場合、開示請求手数料が必要になります。
基本的に、CICでは1回の開示請求に500円、JICCの場合は1,000円程度が手数料となっています。
そして、支払い方法ですが、各信用情報機関によって異なり、クレジットカード決済や銀行振込が利用可能です。
また、必要書類として、事前に運転免許証や健康保険証、パスポートなどが必要になります。
これらの書類は、提出方法(オンラインまたは郵送)に応じてコピーまたは画像データとして提供します。
開示請求後の情報取得までの期間
開示請求を行ってから情報を取得するまでの期間ですが、これは利用する方法によって異なります。
スマホを含むインターネットを利用した場合には、手続きが完了したその日のうちに結果が確認出来る場合があります。
また、郵送で請求した場合は、信用情報機関が書類を受領してから情報を送付するまでに通常1週間程度掛かります。
このように、信用情報の取得可能なタイミングは、利用する方法や混雑具合によって異なるため、余裕をもって手続きを行う必要があります。
信用情報開示で得られる情報
ここでは、個人信用情報機関への信用情報開示請求で得ることが出来る情報について解説します。
契約内容と支払い履歴
信用情報開示を行うことで、過去および現在のクレジット契約内容や支払い履歴を確認することが出来ます。
例えば、自分名義で契約したクレジットカードやローンの契約日、契約金額、返済開始日などが記載されています。
また、支払いの遅延や完済状況なども詳細に記録されており、これら情報は個人の信用力を示す重要なデータとして審査の際に金融機関へ提供されます。
延滞や事故情報の確認
信用情報に登録される「延滞」や「事故情報」も、開示請求で確認することが出来ます。
例えば、クレジットカードやローンの返済を長期間滞納した履歴や、債務整理を行った場合の情報がこれに含まれます。
このような履歴が登録されている場合、今後新しいクレジット契約やローン審査に通らない可能性が高くなります。
そのため、クレジットカードやローン審査に不安がある人は、申し込み前に信用情報に金融事故情報が登録されているのか?の確認が必要です。
クレジットカードの利用状況
クレジットカードの利用状況についても、信用情報には詳細に記載されています。
現在利用中のクレジットカードやショッピング枠、キャッシング枠の使用状況を把握することが出来ます。
これにより、自分の返済可能額や与信枠が適正なのか?について確認可能です。
借入残高やローン契約状況
信用情報には、現在の借入残高や全てのローン契約に関する情報も登録されています。
特に、住宅ローンや自動車ローンなどの長期的な借入れについては、元金残高や返済期間、利率なども閲覧することが出来ます。
これにより、借入全体のバランスを把握し、過剰な借入れを避けることが可能です。
信用スコアの確認
信用情報を開示すると、個人信用情報機関が管理するデータを元にした信用スコアを間接的に確認することが出来ます。
このスコアは、クレジットカード会社や金融機関が新しい契約について審査する際の参考データとなります。
ちなみに、スコアの内容は一部機関によって異なりますが、支払い状況や借入金額、延滞履歴などが評価基準となります。
信用スコアを把握することで、金融取引をスムーズに行うための準備を行うことが可能です。
まとめ
個人信用情報機関に登録されている信用情報には、私たちの金融商品利用情報が登録されています。
そして、この信用情報は誰でも個人信用情報機関へ開示請求を行うことにより確認することが出来ます。
特に、各種金融商品の審査に不安のある人は、審査前に開示請求を行った方が良いです。
また、その請求方法ですが、インターネットまたは郵送によって行い、本人確認書類や開示手数料が必要になります。
ちなみに、すぐに信用情報を確認したい場合には、インターネットからの申し込みが早いです。