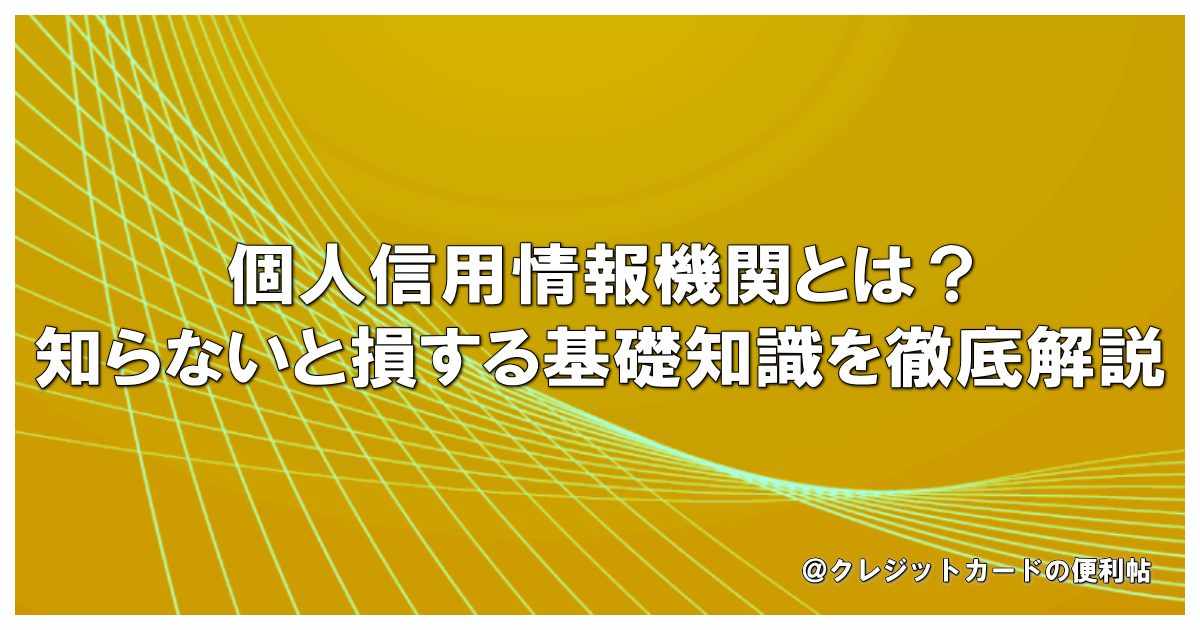クレジットカード審査に申し込む際、「個人情報の取り扱いに関する同意条項」を確認すると思います。
この同意条項の中に、個人信用情報機関としていくつか名称が記載されています。
カード審査では、ここに記載されている個人信用情報機関に問い合わせを行い、申込者の金融情報を照会します。
その結果、特に問題がなければ、審査に通る可能性が高くなるのです。
ただ、この個人信用情報機関というものが、一体どういった組織なのか?分からないという人が一定数います。
そこで、当記事では個人信用情報機関とは?知らないと損する基礎知識を解説します。
個人信用情報機関の基本概要

まずは、個人信用情報機関の基本について解説します。
個人信用情報機関とは?
個人信用情報機関とは、消費者のクレジットやローンに関する情報を収集・管理し、その情報をクレジット会社や金融機関などの加盟会員に提供する機関のことです。
これにより、貸し手側(各種金融機関)は利用者の信用力を適切に判断し、無理のない契約を提供することが可能になります。
また、これらの機関に登録される情報は、契約者本人の同意が得られた場合に限り利用されます。
基本的には、クレジットカードや各種ローン申し込み書に同意条項として記載されているため、申し込み=同意した事になります。
そして、個人信用情報機関は貸金業法や割賦販売法に沿って運営されており、その取り組みを通じて信用市場の健全性を支えています。
どんな情報が登録されるのか?
個人信用情報機関には、利用者の氏名や生年月日、住所などの基本的な個人情報が登録されます。
それに加えて、契約内容(例えば契約金額や契約日、最終返済日など)や支払状況、残高情報などが詳細に登録されます。
これらの内容には、延滞の記録や代位弁済が発生した場合の情報も含まれますので注意が必要です。
ただ、個人信用情報機関には、金融情報以外の人種や宗教など個人に関する敏感な情報は登録されません。
指定信用情報機関とその他の機関の違い
指定信用情報機関とは、国の法律で定められた条件を満たし、消費者信用情報の管理・提供を適切に行う認定を受けた機関を指します。
これには、クレジット会社や銀行など各種金融機関が利用しやすい体制が整備されています。
代表的な指定信用情報機関には、「株式会社シー・アイ・シー(CIC)」や「株式会社日本信用情報機構(JICC)」があります。
その一方、それ以外の個人信用情報機関は、特定の業界や地域に限定された用途で信用情報の管理を行うことが多いです。
例えば、金融以外の業界で利用されることもあり、扱う情報の範囲や仕組みに違いが生じます。
指定信用情報機関は、全国的な規模で信用市場全体を支える役割がある一方、その他の機関は特定の分野に特化している点が異なります。
信用情報がどのように利用されるのか
個人信用情報機関に登録されている信用情報は、主にクレジットカードやローン契約の審査において重要な判断材料となります。
クレジット会社や金融機関は、申請者の支払能力や返済状況を確認するために信用情報を照会します。
これにより、契約者が過剰な借り入れを行わないよう適正な審査を行うことが可能になります。
また、信用情報は信用取引の安全性を高める手段としても活用されます。
例えば、延滞や債務整理といった情報を共有することで、加盟会員はリスクを回避しつつ、利用者に適した金融商品を提供することが出来ます。
そのため、消費者にとっても重要なコミュニケーションツールの役割を果たしているのです。
主な個人信用情報機関
ここでは、日本国内における主な個人信用情報機関について解説します。
CIC(指定信用情報機関)
CIC(株式会社シー・アイ・シー)は、日本の代表的な個人信用情報機関の1つであり、1984年にクレジット会社を中心とした共同出資で設立されました。
CICは、割賦販売法および貸金業法に基づき、指定信用情報機関としての役割を担っています。
主に信販会社や百貨店、リース会社、消費者金融が加盟し、クレジット契約において重要な信用情報の収集・管理・提供を行っています。
そこで、CICに登録される主な情報としては、氏名、生年月日、住所、契約内容(ローン金額、返済状況など)が挙げられます。
消費者が住宅ローンやクレジットカードを申し込む際、支払い能力を判断するために、加盟会社がCICの信用情報を利用しています。
JICC(株式会社日本信用情報機構)
JICC(株式会社日本信用情報機構)は、日本最大規模の個人信用情報機関の1つです。
信販会社や消費者金融、クレジットカード会社など、広範囲の業界に対応しています。
加盟会員の業種の多様性が特徴であり、特に消費者金融やカーローンなどの情報収集・管理を得意としています。
JICCでは、契約内容や返済履歴などの情報に加え、支払いの延滞や自己破産といったネガティブな信用情報を管理しています。
また、自分の信用情報を守るため、本人申告制度を提供しており、盗難や詐欺などの対策として活用されています。
KSC(全国銀行個人信用情報センター)
KSC(全国銀行個人信用情報センター)は、銀行や信用金庫、信用組合などの金融機関が主に加盟する個人信用情報機関です。
主に、住宅ローンや自動車ローンといった高額ローンを対象に、信用情報の登録・提供を行っています。
KSCは、他の機関との相互交流を活用し、消費者が複数の金融機関でクレジットを利用する際の情報を正確に共有しています。
これによって、多重債務や貸し倒れのリスクを軽減する役割を担っています。
また、金融商品に伴う信用情報を長期にわたって管理する点も特徴です。
各信用情報機関の違いと使い分け方
CIC、JICC、KSCの3つの個人信用情報機関には、それぞれの特徴と役割があります。
CICは、主に信販会社や消費者金融を対象とした信用情報の管理に特化しており、クレジットカードや小口ローンを利用する際に使われます。
そして、JICCは信販や消費者金融に加えて、自動車ローンや少額融資の情報もカバーし、幅広い業種を対象としている点が特徴です。
また、KSCは主に銀行や信用金庫が加盟しており、住宅ローンや事業性融資など、高額取引の信用情報管理に特化しています。
これらの機関は相互連携を行っているため、1つの信用情報機関に登録された情報が他機関にも間接的に影響を与える場合があります。
消費者としては、自分の利用する金融商品や取引内容に応じて、どの信用情報機関に自分の情報が登録されているかを把握する必要があります。
そして、必要に応じてこれらの個人信用情報機関へ開示請求を行うことも必要になります。
個人信用情報機関と私たちの生活への影響

ここでは、個人信用情報機関が私たちの与える影響について解説します。
クレジットカード審査やローン申し込みへの影響
個人信用情報機関では、消費者の信用情報を管理し、クレジット会社や金融機関に提供しています。
この情報は、クレジットカードやローンの申し込み時に審査基準として活用されているのです。
そして、信用情報には過去の支払履歴や契約内容、延滞情報などが登録されているため、これらの情報が審査結果に大きく影響します。
例えば、支払いの遅延や債務整理の記録がある場合、それがマイナス評価となります。
その結果、クレジットカードの発行やローン契約が難しくなる場合があるため注意が必要です。
信用情報の管理とそのメリット
個人信用情報機関の信用情報が適切に管理されることにより、金融取引における安心感を得ることが出来ます。
クレジット会社や銀行では、この信用情報を活用することで、顧客の支払能力を適切に判断し、契約におけるリスクを軽減することが出来ます。
これにより、消費者側でも適切な範囲でクレジットカードやローンを利用できる環境が整います。
また、信用情報の利用は消費者にとってもメリットがあり、良好な信用履歴を持つことで、将来より良い条件での金融取引が可能となります。
信用情報に傷がつく原因
信用情報に傷がつく主な原因には、クレジットカードやローンの延滞、債務整理、自己破産手続きなどがあります。
こうした情報は個人信用情報機関に登録され、一定期間保存される事になります。
その結果、延滞や自己破産情報が登録されている期間は、新たな金融商品の契約が難しくなります。
例えば、延滞情報は支払いを完了した日から約5年間保持されるため、その影響で新しいクレジットカードやローンの審査が通らない可能性が高くなります。
このような状況を避けるためにも、クレジットカードや各種ローンの支払いは延滞無く行う必要があります。
信用情報を健全に保つためのポイント
信用情報を健全に保つためには、以下3点のポイントに注意することが重要になります。
- 必ず支払期日を守ること
- 無理な借り入れは避けること
- 定期的な信用情報のチェックを行うこと
特に、個人信用情報機関へ定期的に開示請求を行うことは重要です。
定期的に自分の信用情報を確認することで、誤った情報が登録されていないかをチェックすることが出来ます。
これにより、自分にとってマイナスになる登録を未然に防ぐ事が出来るため、今後金融商品を利用する際に有利になります。
まとめ
個人信用情報機関とは、消費者の金融商品利用情報=信用情報を登録・管理している機関です。
この信用情報には、消費者の住所や氏名のほかに、延滞を含む支払い情報や残高情報なども登録されています。
そして、信用情報に良好な支払情報が登録されていると、クレジットカード審査では有利になります。
その反対で、信用情報にネガティブな情報が登録されていると、クレジットカード審査に通らない可能性が高くなるため注意が必要です。